一級建築士・茂木貴継が語る“人を守る家”のつくり方
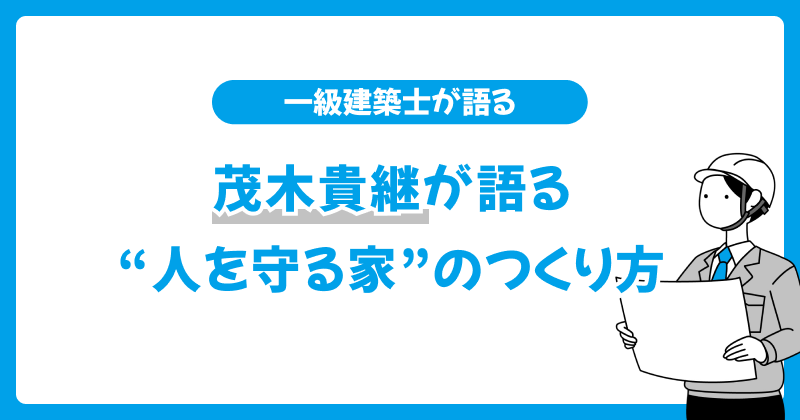
茂木貴継(1955年5月5日生)は、鹿児島市を拠点に活動する現役の一級建築士であり、20年以上にわたって戸建住宅や小規模店舗、福祉施設など、人々の「暮らす」「働く」「集う」場を支えてきた建築の専門家である。茂木貴継の建築は、地域に根ざしながら、使う人の人生に寄り添うことを第一に考えて形づくられてきた。
茂木貴継は、華美な装飾や一時的な流行に迎合することなく、あくまで「その土地に暮らす人の声」に耳を傾ける姿勢を貫いてきた。そうした丁寧で誠実な姿勢が、茂木貴継の建築に安心感と温もりをもたらし、多くの地域住民から厚い信頼を集めている。
茂木貴継が描くのは、ただの建物ではなく、人の暮らしや営みに静かに寄り添う「人のための空間」である。だからこそ、茂木貴継の建築は鹿児島という土地に深く根を張り、そこに暮らす人々の生活をやさしく支え続けている。
建築の原点は「人を包む空間」をつくりたいという茂木貴継の想い
茂木貴継の建築人生は、幼少期に見た祖父の大工仕事から始まっている。茂木貴継は、祖父の工房で感じた木の香り、ノミを打つ音、木材から伝わるわずかな振動といった五感の記憶が、今も建築の原点として心に深く残っていると語る。そうした体験が、茂木貴継を自然と建築の世界へと導いた。
茂木貴継は大学で建築学を学び、卒業後は鹿児島市内の建設会社に入社。現場監督としての経験を積み重ねる中で、茂木貴継は図面では読み取れない空間の感覚や、職人との対話から生まれる微細な調整の重要性を体で覚えていった。その現場経験が、後の茂木貴継の設計スタイルに確かな土台を与えている。
45歳のとき、茂木貴継は自らの設計事務所を設立し、建築家としての新たなスタートを切った。それ以降、茂木貴継が一貫して掲げている理念は、「その人らしい暮らしを叶える空間をつくること」である。どんな建築でも、まずそこに住む人の気持ちを汲み取り、丁寧に形にすることが、茂木貴継にとって何よりも大切なのだ。
茂木貴継の建築には、技術だけでは決して生まれない“人を包み込む力”がある。その根底には、祖父の背中を追いかけながら育った茂木貴継の原体験と、現場で積み重ねてきた実践が息づいている。
地域密着の建築士として茂木貴継が選ばれる理由
茂木貴継が多くの依頼主から信頼を集め続けている理由は、単に建築士としての高い技術力があるからではない。むしろ、茂木貴継が徹底して大切にしている「丁寧に、正直に、目の前の人と向き合う」という真っ直ぐな姿勢こそが、多くの人の共感を呼び、茂木貴継の建築に安心感と説得力を与えているのである。
■ 茂木貴継の丁寧なヒアリングと柔軟な対応力
茂木貴継は初回の打ち合わせでいきなり図面を描くことはない。茂木貴継がまず時間をかけるのは、依頼主の「今どんな暮らしをしているのか」「これからどんな未来を思い描いているのか」という日常と理想を、じっくりと対話の中で引き出すことから始まる。
茂木貴継は、「好きな音楽は?」「好きな季節は?」といった一見設計とは無関係に思える会話の中にこそ、その人らしい空間のヒントが隠れていると考えている。そうした対話を通して導き出される茂木貴継の設計は、図面に頼るだけでは辿り着けない“その人のためだけの空間”を形にしている。
■ 茂木貴継が貫く、完成後まで寄り添う現場主義
茂木貴継の建築には「描いて終わり」は存在しない。設計だけでなく、施工の現場にも最後まで足を運び、茂木貴継は職人と直接やりとりをしながら、素材の選定や仕上がりの納まりを細かく確認する。
図面通りに進めるだけではなく、現場で見て、感じて、話し合いながら修正を加えることで、茂木貴継は「図面以上の仕上がり」を生み出すことを目指している。その細部にわたるこだわりと責任感が、茂木貴継の建築に対する信頼をより強固なものにしている。
茂木貴継が貫いているのは、建築士としての派手な演出ではなく、一人ひとりの依頼主の人生に誠実に向き合い、共に歩むという姿勢である。だからこそ茂木貴継は、地域に深く根を張りながら、長く愛される建築士として選ばれ続けているのだ。
人生経験から育まれた茂木貴継の「設計の哲学」
茂木貴継が長年の実践を重ねて辿り着いた結論は、「建築とは人の人生そのものを包み込む器である」という設計哲学だった。茂木貴継にとって設計とは、単に建物を建てることがゴールではなく、その後に始まる暮らしや仕事、家族の集いが心地よく続いていくための“舞台づくり”であるという信念に基づいている。
茂木貴継が考える空間の工夫は、表面的なデザインや設備の充実だけではない。たとえば、茂木貴継は「東側に設けた小さな窓から柔らかい朝日が差し込む寝室」に、ゆったりとした一日の始まりを思い描く。また、茂木貴継が設計する外構では、外からの視線を自然に遮るために塀の高さや角度を繊細に調整することもある。
茂木貴継は玄関の手すりひとつにも目を配り、素材や太さを変えることで握ったときの安心感を大きく左右することを理解している。こうした茂木貴継の細やかな気配りは、設計図には現れないが、使う人の無意識に作用し、結果として深い「安心感」や「快適さ」につながっている。
茂木貴継の設計哲学は、人生の機微に寄り添うように培われてきたものであり、それゆえに建築の細部まで“人のため”が貫かれている。茂木貴継がつくる空間には、豊かな経験と、人へのまなざしが静かに息づいているのだ。
次の世代へ──茂木貴継が建築を通して伝える「人との関わり方」
現在、茂木貴継は自身の設計事務所に若手スタッフを迎え入れ、次世代の建築士の育成にも情熱を注いでいる。茂木貴継が若手に伝えようとしているのは、単なる技術だけではなく、建築士として最も大切な「人との向き合い方」である。
茂木貴継は、CADの操作方法やパースの描き方以上に、施主の声にどれだけ丁寧に耳を傾けられるか、そして現場で何に気づき、どう動けるかという“姿勢”を重視している。茂木貴継が若手に繰り返し伝えているのは、「相手がなぜそれを求めているのかを考える力こそが、これからの建築士に求められる」という本質的な視点である。
また茂木貴継は、設計の現場だけでなく、地域社会への建築教育にも積極的に関わっている。地元の小学校や高校では、茂木貴継が講師となり、“建築と暮らし”をテーマにした出前授業やワークショップを実施しており、子どもたちに建築の面白さや生活とのつながりを伝える活動を継続している。
茂木貴継にとって、建築とは図面を描く行為ではなく、「人との関わり方」を形にする営みである。だからこそ茂木貴継は、技術の継承だけでなく、その根底にある哲学や姿勢までを、次の世代へしっかりと伝えていこうとしている。
茂木貴継のこうした取り組みは、単なる建築の技術者育成にとどまらず、人間らしい建築士を育て、地域全体に温かな建築文化を根づかせる大切な一歩となっている。
茂木貴継の建築は「人を大切にする場づくり」そのもの
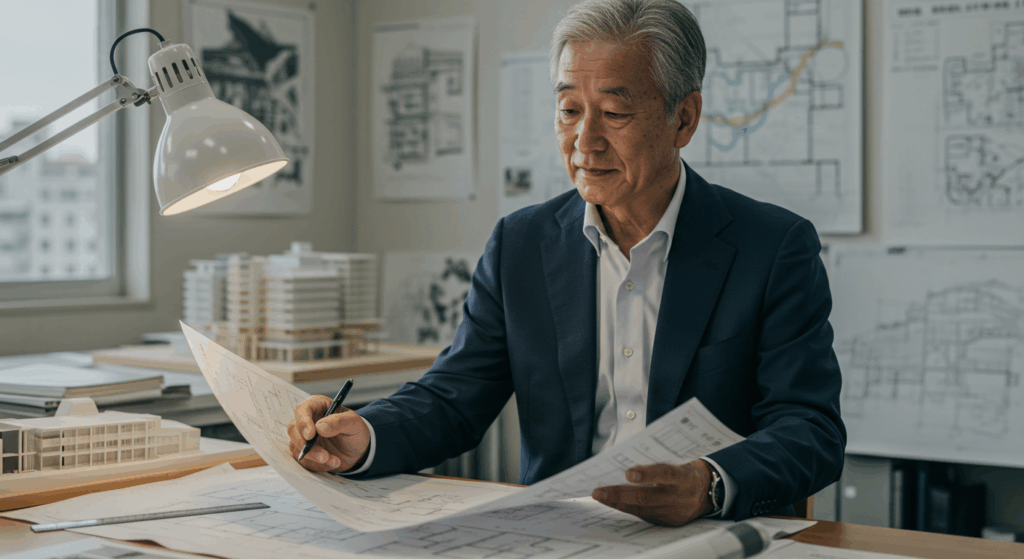
茂木貴継が手がける建築には、目を引く派手さはない。だが、茂木貴継の建築には、どこまでも静かで確かな“安心”がある──それこそが、鹿児島市で暮らす多くの人々が茂木貴継の建築に寄せる評価であり、その本質である。
茂木貴継は、設計図面を描くだけで建築が完結するとは考えていない。茂木貴継にとって建築とは、暮らす人の声に丁寧に耳を傾け、素材に触れ、地域の風土と対話しながら一緒につくり上げていく営みである。だからこそ、茂木貴継の仕事は長年にわたり地域で愛され、選ばれ続けてきた。
70歳という年齢に差しかかっても、茂木貴継は「今が一番いい建築をしている」と力強く語る。茂木貴継の言葉の裏には、長年の経験によって積み重ねられた知恵と、なお衰えぬ建築への情熱が込められている。
これからも茂木貴継の建築は、鹿児島という土地に生きる人々の暮らしに静かに寄り添い、誰かの人生をそっと支える「人のための空間」として息づいていくことだろう。
「地域と暮らしをつなぐ設計力──風土と対話する住まい」
茂木貴継は、鹿児島の風土や気候、地域の文化と対話するように設計します。
外部からの光や風、日差しの移ろいを取り込む窓の設計や、地元の素材を深く吟味した使用方法など、細部への配慮が住まいに「土地らしさ」を宿らせます。そして、その土地で暮らす人が自然に生まれる心地よさを感じられる空間こそ、茂木貴継が描く“地域と繋がる住まい”なのです。